もしかしたら今、子どもが泣き叫ぶ声がまだ頭の中に響いていて、途方に暮れながらスマホを手に取ったのかもしれません。
また怒ってしまった。 思い通りにいかない自分にがっかりしている。 誰かに助けを求めたいけれど、それもできずに、ただ検索バーに「子ども 癇癪 疲れた」と打ち込んだ。
その行動だけでもう、あなたは十分がんばっています。
…このページを見つけてくれて、ありがとうと伝えたいです。
私自身、子どもの癇癪に何度も心が折れそうになった経験があります。 寝かしつけの後、暗い部屋の中で泣いた夜も、声を荒げた自分に嫌気がさした日もありました。
だから、今あなたがどんな思いでここにいるか、少しだけ想像できます。 あなたが悪いわけじゃない。 うまくできなくて当たり前。 今ここにいるあなたに、少しでもやさしい時間が訪れることを願って、この言葉を届けます。
癇癪の真っ只中にいるあなたへ——それは「あなたのせい」じゃない
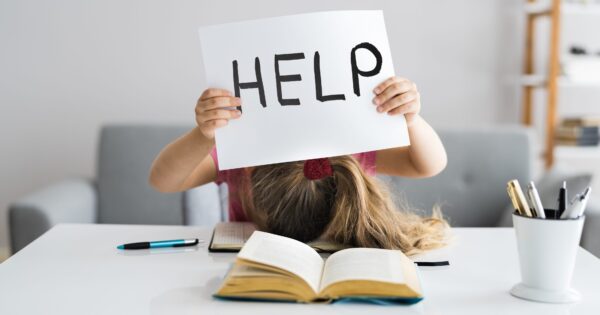
子どもが突然泣きわめき、叫び、物を投げる。近くにいれば叩かれることもあるし、公共の場では人の視線に晒されて冷や汗が出る。
何が引き金になるのかも分からない。昨日は大丈夫だったのに、今日は同じ場面で大爆発。朝は笑顔だったのに、夕方には怒鳴り声と涙の渦の中。そんな日々をくぐり抜けていると、「私の育て方が間違っていたのかも」と、自分を責めたくなってしまいます。
でも、どうか知っていてほしいのです。 癇癪は「感情の整理方法」がまだ育っていない子どもが、何とかして自分を保とうとする姿でもあります。わざとやっているわけでも、あなたを困らせたいわけでもありません。
私自身、どうして泣いているのか分からず立ち尽くしたことがあります。声をかけるたびに「うるさい!」というような態度を返され、こちらも泣きたい気持ちになった日もありました。正解が分からないまま、それでも毎日向き合っていました。
■ 癇癪が起きる背景には、こんな要因があります
- 言葉で気持ちを伝える力がまだ未熟
- 「こうしたい!」という意志が強くなるタイミング(イヤイヤ期や自我の芽生え)
- 眠気や空腹などの身体的ストレス
- 集団生活での緊張や頑張りの反動
- 安心できる人の前でだけ出せる“感情の解放”
癇癪をぶつけてくるのは、子どもにとって「この人なら受け止めてくれる」と感じている証です。外ではがんばっている子が、家に帰って本当の姿を出せる場所。それがあなたなのです。
でも、それでもつらいものはつらい。暴言や暴力的な行動を目の前で受け止め続けるのは、誰にとっても過酷なことです。
「信頼されているから」と頭で理解していても、心が追いつかないこともあります。 そんな日は、「つらい」「もう限界」と思っていい。むしろ、それを感じられるあなたは、まだ子どもに向き合おうとしている証でもあります。
あなたの気持ちも、どうか大切にしてください。 癇癪への対応は、まず“自分のつらさに気づく”ことから始めていいのです。
ついしてしまう反応も、がんばってきた証拠です

癇癪の対応を「正解通り」にできる親なんて、いません。 本やネットに書かれているように“落ち着いて受け止める”なんて、毎日毎回できるものではないですよね。
頭ではわかっていても、現実の育児は想像以上に体力も気力も使います。 泣き声のボリューム、繰り返される行動、予測不能なスイッチ… 疲れている日には、心のキャパシティが一瞬であふれてしまうこともあります。
だからこそ、こんな反応が出てしまっても、それは自然なことです。
- つい怒鳴ってしまった
- 少し距離を取ろうと無視してしまった
- なぜそんなに怒っているのか、問い詰めてしまった
それは「無関心だから」ではなく、「どうにかしたい」「ちゃんと向き合いたい」と思っているからこそ生まれる反応です。
そして、これまでなんとかやってこられたこと、今日も子どもに向き合っていること。 それ自体が、がんばってきた証拠です。
他の家庭と比べて落ち込む必要なんてありません。 よその子が穏やかに見えるのは、その一瞬だけかもしれないし、見えないところで同じように悩んでいるかもしれない。
あなたの子育ては、あなたと子どもだけのかけがえのない関係性の中にあります。
完璧じゃなくていい。 感情をぶつけてしまったあと、また向き合おうとするその姿勢こそが、子どもにとっての安心につながっていきます。
どうか、がんばりすぎている自分に気づいてあげてください。
少しだけ、子どもと離れてもいい

「自分に優しくしましょう」——そう言われても、「優しくなんてできないよ」と思うとき、ありますよね。
実際、癇癪の真っ只中にいるときに、心の余裕も思いやりも持ち合わせていられないことのほうが多い。
だからこそ、「心の余裕を持とう」と頑張るのではなく、まずは“物理的に”子どもと少しだけ距離を取ることが、現実的な対処法になります。
逃げることじゃありません。 育児を放棄することでもありません。
それは、自分の心と身体を守るための“呼吸のためのスペース”です。
私も、癇癪のたびに「また来た…」と肩に力が入り、どうにもならない感情に飲まれそうになったことが何度もあります。 そんなとき、たった3分でもひとりになれたら、気持ちの波がほんの少し和らぐのを感じました。
■ たとえばこんな方法があります
- テレビや動画を見せて、その間にトイレにこもって3分深呼吸する
- 洗面所で手を洗いながら、冷たい水で気持ちを切り替える
- ベランダに出て空を見上げ、数回深く息を吸ってみる
- パートナーや家族に「5分だけ任せるね」と言って、別室に移動する
- 保育園の延長、一時保育を“頼っていいもの”として使ってみる
一息つくことで、視界が広がります。 子どもの泣き声も、さっきより少しだけ遠くから聞こえるようになります。
あなたの呼吸が整えば、子どもに向けるまなざしも整っていきます。 それは、優しい気持ちになれるという意味だけではなく、「反応ではなく、選べる自分に戻れる」ということでもあるのです。
癇癪への具体的な対応のヒント

癇癪は「やめさせるもの」ではなく、「一緒に乗り越えるもの」と考えると、少しだけ肩の力が抜けるかもしれません。
その瞬間は嵐のようで、何をどうしていいかわからなくなることがあります。 でも「完璧に対応しよう」と思わなくて大丈夫です。 あなたが「関わろう」とする、その気持ちだけで、十分価値があります。
ここでは、私自身の経験や多くの保護者の声をもとに、日常の中ですぐに試せる5つのヒントをご紹介します。
■ 今すぐできる5つの関わり方
- まずは安全の確認と、そばにいること
子どもが物を投げたり叩いたりする場合は、まず周囲の安全を確保。無理に話しかけたりなだめようとしなくても、「そばにいるよ」という気配だけで子どもは安心します。怒りや混乱の真ん中にいる子どもには、言葉より“存在”のほうが届きやすいのです。 - 気持ちを代弁する
「悔しかったんだね」「思い通りにならなくて嫌だったんだね」など、子どもがうまく言葉にできない気持ちを、代わりに言語化してあげましょう。「自分の気持ちをわかってくれる人がいる」という感覚は、落ち着きの土台になります。 - 癇癪が落ち着いてから伝える
大声や暴力に対して注意したいときも、癇癪の真っ最中には避けましょう。落ち着いたあと、「叩かれるとママは痛いよ。でも気持ちは伝わったよね」と、シンプルな言葉で伝えるのが効果的です。 - 先回りして“見通し”をつくる
「あと5分でおしまいだよ」「このあとお風呂に行こうね」など、行動の予告があるだけで、切り替えがスムーズになります。突然の変化に弱い子どもには、次の行動が見えていることが安心材料になります。 - “癇癪になりにくい環境”を整える
睡眠不足、空腹、疲れ、予定の詰め込みすぎ——こうした条件は癇癪の引き金になりがちです。「不機嫌になる前に予防する」という視点で、生活リズムを見直してみるのもひとつの手です。
一人でがんばらなくていい——外の手を借りてみよう

癇癪が続くと、「私がどうにかしないと」「私さえ我慢すれば」と、自分ひとりで背負い込みがちです。 でも、育児はひとりで完結できるものではありません。
むしろ、“誰かに頼ること”が、あなたと子どもを守るためにとても大切な選択です。
周囲に頼ることに、罪悪感を抱く必要はありません。 あなたが疲れ果ててしまう前に、手を差し伸べてくれる場所はたくさんあります。
「助けを求めるのが苦手」「どこに頼ればいいかわからない」——そんなときは、まず1つだけ、気になったところにアクセスしてみてください。
「話すだけ」で気持ちが軽くなること、本当にあります。
■ 相談できるところ一覧
- 保育園・幼稚園の先生:家庭とは違う時間の中での子どもの姿を見てくれています。思わぬ一面や頑張りを教えてくれることも。
- スクールカウンセラーや保健師:発達の特徴や気質に合わせた対応方法について、一緒に考えてくれます。"発達"という言葉に構えず、安心して相談して大丈夫です。
- 子育て支援センターや一時保育:子どもと離れる時間をつくるために活用できます。親がリフレッシュすることも、立派な育児の一部です。
- 電話相談やLINEチャット:直接話すのがつらいときは、匿名で話せる・文章で気持ちを伝えられる窓口もあります。時間外でもつながる支援があります。
子どもと一緒に、自分も育て直していい

癇癪は、「親が正しく導くべき課題」ではありません。
思い通りにならない現実に、子どもも親も感情をぶつけあいながら、どうにか前に進んでいく。そんな“ぶつかり合い”の中で、実は一緒に育ち合っているのだと思います。
「今日は怒らずにいられた」 「怒ったけど、あとで謝れた」 「昨日よりもほんの少し、深呼吸が早くできた」
——それらは、誰かに褒められることもないし、目に見える成果でもありません。でも、確かに“変化”であり“前進”です。
子どもが毎日少しずつ成長しているように、親だって日々育ち直している。
「こんな対応をしてしまった自分はダメだ」と過去を責めるのではなく、 「明日は少し違う自分で向き合えるかもしれない」と、未来をつくっていく感覚でいていいのです。
完璧を目指さなくていい。 “うまくできなかったけど、また向き合おうとしている”——その姿こそが、子どもにとって何よりの安心になります。
育児は、昨日できなかったことが、今日ほんの少しできるようになる営み。 それは子どもも、大人も同じです。
まとめ|あなたが今日、ここにたどり着いたことがすごいこと

また怒ってしまった。 また泣かせてしまった。 そんな後悔の中で、あなたはここに来てくれました。
それは、「あきらめていない」ということです。 そして、「もう少し、なんとかしたい」と、誰にも見えないところで、静かに自分を立て直そうとしているということです。
すぐに理想の対応なんてできなくて当然です。 でも今日、言葉を探し、ここまでたどり着いた。 それだけで、もう充分すぎるほどに愛のある行動です。
どうか、今日1日を生き抜いた自分に、ほんの少しでもやさしいまなざしを向けてあげてください。
誰かのためじゃなく、あなたのために。
明日、ほんの少しでも呼吸がしやすくなっていますように。